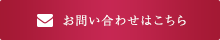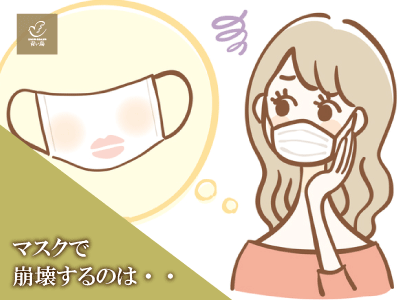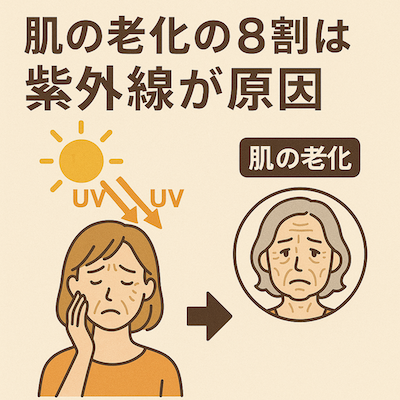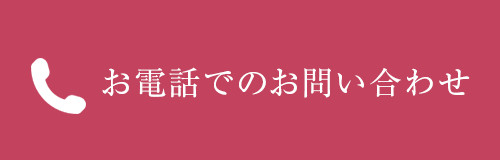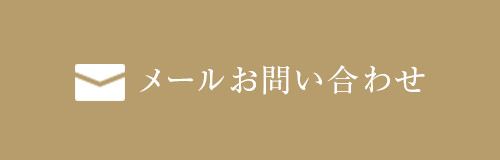ニキビ治療の落とし穴:「治った」と思っても高いニキビ再発リスク
私が美肌治療を行う中でしばしば障害となるのが「ニキビ」です。
せっかく表面のブツブツが消えても、赤い炎症が長引いたり、茶色い色素沈着が残ったりして、それまでの美肌治療を台無しにしてしまうことがよくあります。
しかも驚くべきことに、大多数の方が皮膚科でのニキビ治療を受けていません。
日本の皮膚科診療における「ニキビ治療」には、以下の3つの大きな課題があります:
・受診率の低さ - 多くの方が自己治療に頼っている
・受診の遅れ - 症状が悪化してからようやく来院する
・治療の中断 - 「ブツブツが消えたら治療終了」という誤った認識
特に3つ目の「治療の中断」は深刻な問題です。「表面的な症状が改善したから」という理由で自己判断で治療を中止すると、待ち受けているのは残念ながらニキビの再発です。
ニキビができやすい肌質は簡単には変わりません。そのため、ニキビ再発防止には症状が落ち着いた後も長期的な治療継続が不可欠です。「ニキビがひどくなった時だけ皮膚科へ」という悪循環から抜け出すためには、この基本的な認識を改める必要があります。
ニキビ再発防止のために治療を継続する科学的根拠
ニキビ再発防止を目指した治療の継続には、明確な科学的根拠があります。エピデュオ・フォルテ(アダパレン0.3%+過酸化ベンゾイル2.5%)を用いて、患者に6ヶ月間この薬剤を塗布した研究報告があります。
この報告の特筆すべき点は、塗り薬を続けることで、ニキビ跡の数を減少させたことですが、もう一つ注目すべきは治療が3ヶ月、6ヶ月、1年と継続するにつれて効果が向上ていたこと。これは、治療を継続することで、ニキビの再発防止だけでなく、ニキビ跡の減少にもつながる可能性を示唆しています。
日本で実践できるニキビ再発防止対策
残念ながら日本ではエピデュオ・フォルテは未承認ですが、類似製剤であるエピデュオゲル(アダパレンの濃度が0.1%と低い)においても、半年間の継続使用で:
・新たなニキビ発生の防止(ニキビ再発防止)
・既存のニキビ跡の改善
という二重の効果が確認されています。やはりニキビ再発を防ぐための維持療法が、肌質そのものの改善につながる可能性が示唆されました。
ニキビ再発防止の観点からは、少なくとも1年間の治療継続を強くお勧めします。この期間を経て、中止する明確な理由がなければさらに継続することで、新規ニキビの予防と既存の瘢痕改善という二重のメリットが期待できます。
本当の「ニキビ治療」とは:再発防止のための維持療法が鍵
日本皮膚科学会のガイドラインでも明記されていますが、真のニキビ治療には2つのステップがあります:
⚪️急性期の炎症を抑える「急性期治療」
⚪️ニキビが落ち着いた後の「維持療法」
多くの方が見落としているのは、この2番目のステップです。ニキビ再発防止のための「維持療法」は、ニキビ治療に欠かせない最後の仕上げなのです。
具体的には、アダパレン(ディフェリン)やBPO製剤などの外用薬を継続的に使用することが推奨されています。つまり、「ブツブツが消えたら終わり」ではなく、その後もニキビ再発させないための「維持療法」を続けることが正しいニキビ治療です。
この維持療法の考え方はガイドラインで示されているにもかかわらず、一般には十分に浸透していません。もしかすると医療費増加への懸念から積極的な周知が控えられているのではと疑いたくもなりますが、維持療法の重要性は、皆さんの肌の健康のためにもっと広く認識されるべきではないでしょうか。皮膚科ドクターと相談しながら、あなたに最適な維持療法を見つけてください。
おすすめの関連ブログ記事
(参考文献)
1)Adapalene 0.1%/benzoyl peroxide 2.5% gel reduces the risk of atrophic scar formation in moderate inflammatory acne: a split-face randomized control trial
Dréno B,et al.
JEADV
2017;31:737-742
2)Prevention and reduction of atrophic acne scars with adapalene 0.3%/benzoyl peroxide 2.5% gel in subjects with moderate or severe facial acne: results of a 6-month randomized, vehicle-controlled trial using intra-individual comparison
Dréno B,et al.
Am J Clin Dermatol.
2018;19:275-286
3)Long-term effectiveness and safety of up to 48 weeks' treatment with topical adapalene 0.3%/benzoyl peroxide 2.5% gel in the prevention and reduction of atrophic acne scars in moderate and severe facial acne
Dréno B,et al.
Am J Clin Dermatol.
2019;20:725-732

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)
(最終更新日:2025年5月11日)