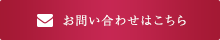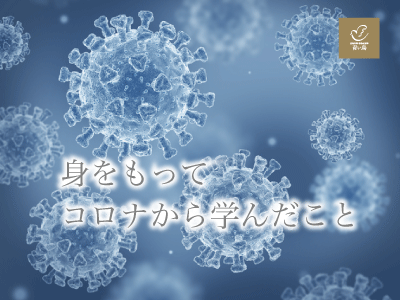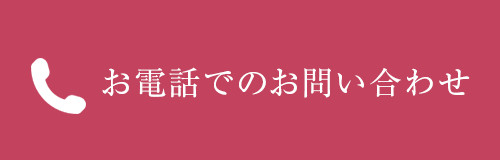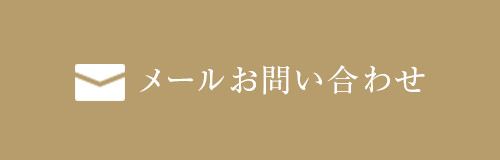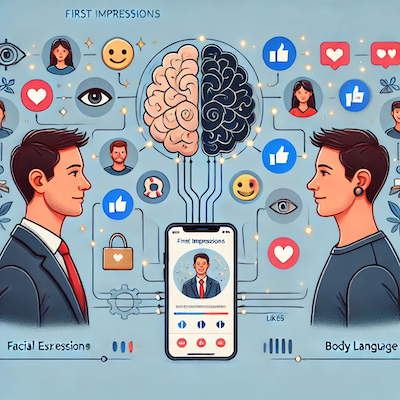
「人は見た目が9割」——この言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。実際、私たちは初対面の人にわずか数秒、場合によっては0.1秒という驚くべき短時間で印象を抱きます。
心理学の研究結果をもとに、第一印象がどのように作られるのか、そして「見た目が9割」という通説の真実について、科学的な視点から解き明かしていきます。
現代のSNS時代における第一印象の変化についても触れながら、私たちが日常的に経験する印象形成のメカニズムを詳しく見ていきましょう。
1.第一印象とは
人は誰かと初めて出会うと、短時間のうちに、その人の見た目や話し方、雰囲気などから「優しそう」、「信頼できそう」、「怖そう」といった印象を持ちます。これが第一印象です。
2.第一印象はいつ、どのようにして作られるか?
「第一印象は会って数秒で決まる」とよく言われます。学術的には、0.1秒で決まる!という報告まであります(文献1)。
その報告では顔写真を 0.1秒/0.5秒/無制限で提示した実験を行い,0.1秒でも無制限に観察した場合と高い相関を示し,極めて短時間で安定した印象が形成されることを実証しました。
これには続報もあり(文献2)、顔写真を見る時間が33ミリ秒を超えると、無制限に観察した場合と判断が一致し始め、167ミリ秒を超えるとそれ以上一致度は改善しませんでした。
私たちが顔の見た目から他者に対する印象を自動的かつ効率的に形成していることを裏付けています。
3.第一印象は見かけが9割!?
2005年に「人は見かけが9割」という題名の本がベストセラーになりました。第一印象の形成においても、「見かけ」、つまりは視覚情報が圧倒的に重要と思えるかもしれません。
こうした場面でよくメラビアンの法則(文献3)が引用されます。
メラビアンの法則とは、人同士のコミュニケーションにおいて、相手に与える影響の割合を示した心理学の法則です。
具体的には、以下の3つの要素が相手に与える影響の割合を表しています:
視覚情報(見た目):55% - 表情、身振り、服装など
聴覚情報(声):38% - 話し方、声のトーンなど
言語情報(話の内容):7% - 実際に話している言葉の内容
この法則は、アメリカの心理学者メラビアンが提唱したもので、「人は見た目が9割」という考えの根拠としても使われています。
注)「人は見た目が9割」の「9割」とは非言語情報が聴覚情報+視覚情報として93%になることが根拠になっています。
「メラビアンの法則」は本来、言語内容と非言語情報が「矛盾している」場合に、受け手がどの情報を手がかりに判断するかを示したもので、メラビアン本人も一般的に当てはめるのは誤用であると、繰り返し指摘しています。
「視覚情報が第一印象の55%を占める」などと説明するのは、明らかに誤用です。
視覚情報――容姿や服装、表情・しぐさなど――は第一印象形成において強力なファクターですが、それだけが全てではありません。言葉遣いや会話の内容、声のトーンといった聴覚・言語情報もまた初期評価に欠かせない要素であり、場合によっては視覚情報以上に重視されるのです。
4.SNSでの第一印象!?
SNSプロフィールやオンライン上の情報に基づく第一印象についても触れておきます。私たちはしばしば、対面で会う前に相手のオンライン上のプロフィールやSNSを見て印象を抱きます。
これについて興味深い研究として、Weisbuchら(2009)は大学生のFacebookページから抱かれる印象と、その学生と直接対面して抱かれる印象が一致するかを調べました(文献4)。
結果、Facebook上で「好感が持てる」と評価の高い学生は、実際に会ってみてもやはり周囲から好かれる傾向が確認されました。
オンラインのソーシャルな世界は、リアルタイムの対人交流とそれほど変わらない可能性があり、SNSプロフィールやオンライン上の情報を参考にすることは、相性の良いパートナー、友人、従業員を見つける上で一定の効果があると結論づけられています。
5.まとめ
第一印象は確かに短時間で形成されます。研究によると、わずか0.1秒という瞬間的な時間でも、私たちは他者に対して安定した印象を抱くことができます。これは人間の持つ驚くべき能力の一つです。
しかし、「人は見た目が9割」という通説については注意が必要です。よく引用されるメラビアンの法則は、言語内容と非言語情報が矛盾している特殊な状況での研究結果であり、一般的な第一印象形成にそのまま当てはめることは適切ではありません。
実際の第一印象形成では、視覚情報(容姿・服装・表情)は確かに重要な要素ですが、それだけが全てではありません。言葉遣いや声のトーン、会話の内容といった聴覚・言語情報も同様に重要な役割を果たします。場面や状況によっては、これらの要素が視覚情報以上に重視されることもあります。
現代のデジタル社会では、SNSやオンラインプロフィールを通じた第一印象も重要になっています。興味深いことに、Facebook上での印象と実際に会った時の印象には一定の相関があることが研究で示されており、オンラインでの第一印象も決して軽視できないものとなっています。
第一印象を良くするためには、見た目だけでなく、話し方や振る舞い、そしてオンラインでの自己表現まで含めた総合的なアプローチが大切だと言えるでしょう。
【参考文献】
1) First impressions: Making up your mind after a 100-ms exposure to a face.
Janine Willis, et al.
Psychological Science
2006;17(7), 592-598
2) Evaluating faces on trustworthiness after minimal time exposure.
Alexander Todorov, et al.
Social Cognition
2009;27(6):813-833
3) Silent Messages
Albert Mehrabian
Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA
1971年
4) On Being Liked on the Web and in the "Real World": Consistency in First Impressions across Personal Webpages and Spontaneous Behavior
Max Weisbuch, et al.
J Exp Soc Psychol
2009;45(3):573-576

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)
(最終更新日:2025年6月29日)