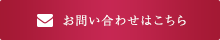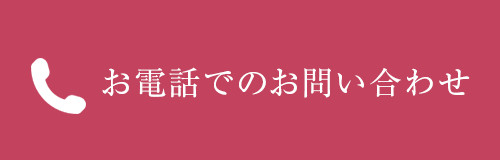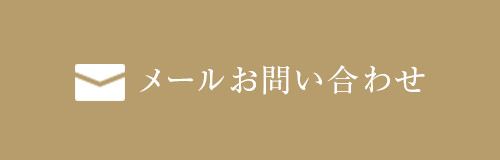結局、美白剤はどれがいいのか?
多くの人が頭を悩ませるこの問いに、生成AIを活用して、純粋に医学的にエビデンスレベルの高い順にランキングを作成しました。
利用したのは、ChatGPT5Proです。網羅的にリサーチして、条件に基づいてランキングを作成することに、もはや人間の出る幕はありません。
このランキングをぜひ美白美容液をお選びのさいに参考にして下さい。なお、生成AIが作成したのはランキングとプロンプトで、それ以外の記事の全ては人間が書いています。
使用したプロンプトは末尾に掲載しています。
複雑なプロンプトになりましたが、要するに美白成分を
1)医学的なエビデンスで評価
2)対象疾患を肝斑、炎症後色素沈着に限定
3)単剤で評価(肝斑でゴールドスタンダードである3剤併用療法を判断から除外する)
4)外用剤に限定(肝斑で内服でも使用されるトラネキサム酸は外用のみで評価する)
することでランキングを作成しました。
あらかじめ、今回のランキングの限界を述べておくと、美白成分は一つの企業が開発し、独占的に市場に展開しているものがいくつもあります(チアミドール、ルシノール、システアミン)が、そうしたケースでは臨床試験も独占している企業から資金ないし資材の提供を受けており、その試験の結果が歪んでいる可能性を否定できません。
今回のランキングではそうしたバイアスが除去できていません。
それではランキングの発表です。
第10位 メチマゾール(製剤名:メルカゾール)
よほどの美容通の方でもメチマゾール(製剤名:メルカゾール)の名前を聞くのは初めてではないでしょうか?メチマゾール(製剤名:メルカゾール)は本来甲状腺疾患で使われている薬です。
◉作用機序:
メチマゾール(製剤名:メルカゾール)は抗甲状腺薬で、チロシンから甲状腺ホルモンが合成されるときの酵素チロシンペルオキシダーゼ(TPO)を阻害しますが、さらにメラニン生成酵素であるチロシナーゼも阻害することが発見されました。
◉ランキングの根拠:
肝斑患者50人を対象とした4%ハイドロキノンとの比較試験(代表文献a)では、ハイドロキノンには劣りましたが、症状の改善が認められました。メチマゾール(製剤名:メルカゾール)は細胞を直接壊す毒性(細胞毒性)はなく、DNAに変異を起こす危険性(変異原性)も低いので、外用薬として長期使用しても比較的安全であり、肝斑治療の代替候補になり得ると結論付けられています。
◉補足コメント:
⚪️今回ランキングの10位に入ったのは、市場には出回っていないメチマゾール(製剤名:メルカゾール)でした。
⚪️現状、承認された美白成分ではないので、市販の製品には配合されていません。あくまで研究・試験的使用の範囲にとどまっています。
⚪️コスメないし医薬品として入手可能な美白成分に限定して、ランキングを作り直そうかとも思いましたが、今回はあくまでエビデンスを最優先することにしました。
⚪️メチマゾール(製剤名:メルカゾール)は何十年も前から甲状腺機能亢進症に使われる成分であり、外用薬として承認されて日の目を見る可能性はありません。
⚪️それよりも可能性が高く現実的なのは、「メチマゾール誘導体」で、すでにコウジ酸や抗酸化物質と結合させた誘導体の開発が進んでいます。
⚪️今すぐではないにせよ、こうした「メチマゾール誘導体」が新規美白成分として、近い将来ドラッグストアで見かけるようになるのではないかと期待しています。
◉代表文献:
a) The efficacy and safety of topical 5% methimazole vs 4% hydroquinone in the treatment of melasma: A randomized controlled trial
Mehdi Gheisari, et al.
J Cosmet Dermatol
2020 Jan;19(1):167-172
第9位 ナイアシンアミド
ナイアシンアミドはビタミンB3の一形態のことで、スキンケアの成分としては美白、シワ改善、皮膚バリア改善、抗炎症、皮脂抑制といった多面的な効果が期待できます。
◉作用機序:
ナイアシンアミドは、他の多くの美白剤とは違い、作用機序がチロシナーゼの阻害(色素の産生をブロックする)ではなく、色素細胞から周囲の角化細胞へのメラニン色素の転送を阻害することで作用します。
◉ランキングの根拠:
肝斑患者27人を対象とした4%ナイアシンアミドと4%ハイドロキノンとの比較試験(代表文献b)では、両群とも症状の改善が認められ、有意差はありませんでした。この試験では病理検査も行われ、ナイアシンアミドが肝斑に特徴的なマスト細胞の浸潤、日光弾性線維症を改善させたことが認められました。
◉補足コメント:
ナイアシンアミドは美白治療において、理想的な併用治療となります。
それは、他の美白剤がチロシナーゼを阻害してメラニンの生成量を減らし、ナイアシンアミドがそれでも作られてしまったメラニンの輸送を妨げることになるからです。
さらに、メラニン色素の茶色系だけでなく、ナイアシンアミドは赤ら顔の赤色系、黄ぐすみの黄色系にも効果を発揮します。
こんなに広範囲に「色」の問題をカバーできるのはナイアシンアミドだけではないでしょうか。
▶クリニックで取り扱うナイアシンアミド10%
◉代表文献:
b) A double-blind, randomized clinical trial of niacinamide 4% versus hydroquinone 4% in the treatment of melasma
Josefina Navarrete-Solís, et al.
Dermatol Res Pract
2011:2011:379173
第8位 タザロテン
日本人には馴染みがありませんが、ニキビ治療薬のディフェリンと同じ合成レチノイドです。
ディフェリンやトレチノインより作用は強力ですが、その分刺激反応も強いというのが米国での評価です。
*当院ではディフェリンを取り扱っています。
◉作用機序:
1. メラニン色素の角化細胞への転送の阻害
タザロテンは、メラニン色素が詰まったメラノソームが、肌の表面の細胞である角化細胞へ運ばれるのを妨げます。
2. 表皮ターンオーバー促進
これによりメラニンを含む角化細胞の排出が促進され、沈着した色素が早く除去されます。
3. 炎症反応の抑制
タザロテンは抗炎症作用を持ち、炎症に伴う色素沈着の悪化を防ぐ効果が示されています。
◉ランキングの根拠:
肌の色が濃い人種に属するニキビ患者74名を対象とした二重盲検ランダム化対照試験(代表文献c)でタザロテン0.1%クリームの効果を評価したところ、タザロテンクリームは肌の色が濃い患者のニキビ跡の炎症後色素沈着の治療に有効でした。
◉補足コメント:
実は当院では以前タザロテンを販売していたのですが、ほとんど売れないまま期限切れを迎えたため、そのまま取り扱いをやめてしまいました。
日本人には強力なレチノイドはハードルが高すぎるのかもしれません。タザロテンには「塗るだけでニキビ跡が治療できる」というとんでもないエビデンスもあるだけに残念です。
タザロテンの当院での取り扱いを再開しました。
タザロテンには、塗るだけの毛穴・ニキビ跡治療という外用療法の新しい可能性を切り拓くポテンシャルがあります。
▶クリニックで取り扱うタザロテン
◉代表文献:
c) Tazarotene cream for postinflammatory hyperpigmentation and acne vulgaris in darker skin: a double-blind, randomized, vehicle-controlled study
Pearl Grimes, Valerie Callender
Cutis
2006 Jan;77(1):45-50
第7位 トラネキサム酸
トラネキサム酸は何かと日本と縁が深い成分。発見したのも日本人なら、1970年代に肝斑がうすくなるという美白効果に気づいたのも日本人です。
◉作用機序:
皮膚にシミができる時には、「プラスミン」という酵素が重要な役割を果たします。
プラスミンは、メラノサイト(メラニンを作る細胞)にメラニンを作らせる様々な「情報伝達物質」の産生を刺激する「スイッチ」のように働きます。
トラネキサム酸はこのプラスミンが作られるプロセスを阻害する働き(抗プラスミン作用)で美白効果を発揮します
◉ランキングの根拠:
複数の臨床試験をまとめて「全体として効果はあると言えるか?」を調べる方法として、「メタ解析」があります。
いくつかあるメタ解析では、肝斑に対するトラネキサム酸外用の評価は揺れていて、最新のメタ解析(代表文献d)では、「他の治療と比較して、優位性が確立されていない」として、さらなる大規模なランダム化比較試験が必要であると指摘しています。
◉補足コメント:
現在、トラネキサム酸は医薬部外品としてのみ配合可能で濃度の上限も2%と定められています。しかし、臨床試験で効果が実証されたのは3〜5%であり、この上限規制がトラネキサム酸が「美白力」を十分発揮できないようにしていると言えます。
そのため現状では医薬部外品のコスメに期待できるのは予防・日常ケアであり、シミ、くすみ、色素沈着の治療目的ならクリニックの医療用医薬品を選ぶといいでしょう。
▶クリニックで取り扱うトラネキサム酸
◉代表文献:
d) Efficacy of Oral, Topical, and Intradermal Tranexamic Acid in Patients with Melasma — A Meta-Analysis
Panchal VS, et al.
Indian Dermatol Online J
2023 Dec 1;15(1):55-63
第6位 システアミン(Cyspera®)
システアミンは、アミノ酸の一つメチオニンの分解を通じてすべての哺乳類の細胞に自然に存在する、人間にとって天然の分子です。その美白作用は1960年代には発見されていました。しかし、独特の非常に強い匂いのため、長年にわたり外用剤の開発は進みませんでした。技術的に匂いを大幅に減らすことに成功したことで製品化にこぎつけました。
◉作用機序:
システアミンの正確な作用機序は完全には解明されていませんが、複合的にメラニン生成を阻害し、暗色のユーメラニンから明るいフェオメラニンへとシフトさせると考えられています。
◉ランキングの根拠:
肝斑に対する5%システアミンと標準的治療であるハイドロキノンの併用療法との比較試験の中には、5%システアミンの方が優れた結果を出したという報告(代表文献e)もあります。
◉補足コメント:
美容皮膚科学の世界において美白剤の優劣は、肝斑のレビュー論文でどう評価されるかが重要な意味を持ちます。
昨年発表されたレビュー文献(代表文献f)には「システアミンは、ハイドロキノンに比べて有効性が劣る可能性があるものの、軽度から中等度の肝斑に対してハイドロキノンに替わる治療の選択肢となりえる。」と書かれています。
◉代表文献:
e) Clinical evaluation of efficacy, safety and tolerability of cysteamine 5% cream in comparison with modified Kligman's formula in subjects with epidermal melasma: A randomized, double-blind clinical trial study
Maryam Karrabi, et al.
Skin Res Technol
2021 Jan;27(1):24-31
f) An Update on New and Existing Treatments for the Management of Melasma
Christian Gan, Michelle Rodrigues
Am J Clin Dermatol
2024 Sep;25(5):717-733
第5位 4‑n‑ブチルレゾルシノール(ルシノール)
日本のポーラが美白成分として研究開発しました。
◉作用機序:
メラニン合成の入り口に当たるチロシナーゼ(メラニン合成の律速段階の酵素)を強力に抑制するとともに、メラニン合成の出口の酵素も抑制します。さらにはチロシナーゼそのものも減らすことで美白作用をもたらします。
分子構造的にレゾルシノールという“骨格”はヒトのチロシナーゼと相性がよく、そのためルシノールやチアミドールのように、この“骨格”をベースにした成分はとても強力(ハイドロキノンより桁違いに強力)に酵素を止められるとされています。
◉ランキングの根拠:
臨床研究は数も質も十分ではありませんが、複数のランダム化比較試験で効果が実証されています。そのうちの一つでは、ルシノールは、臨床的および客観的な皮膚色の評価に基づき、3ヶ月間の治療後、基剤単独と比較して、肝斑の改善に有意な有効性を示しました(代表文献g)。
◉補足コメント:
肝斑の系統的レビューでは、副作用のリスクが低い新規化合物を探求する動きの中で、代替治療薬の一つとして提案されるようになっており、日本発のルシノールも世界的に認知されていると言えるでしょう。
◉代表文献:
g) Evaluation of efficacy and safety of rucinol serum in patients with melasma: a randomized controlled trial
A Khemis, et al.
Br J Dermatol
2007;156(5):997–1004
第4位 トレチノイン
第8位のタザロテンに続いて第4位にトレチノインと、レチノイドが2つランクインしました。
◉作用機序:
1. 表皮ターンオーバー促進
これによりメラニンを含む角化細胞の排出が促進され、沈着した色素が早く除去されます。
2. 炎症反応の抑制
トレチノインは抗炎症作用を持ち、炎症に伴う色素沈着の悪化を防ぐ効果が示されています。
◉ランキングの根拠:
トレチノインを含む3剤併用療法は世界的に肝斑治療のゴールドスタンダードです。ですから、トレチノインというと肝斑のイメージが強いですが、40週間にわたる二重盲検無作為化対照試験で、トレチノインはプラセボと比較して黒い肌に生じる炎症後色素沈着を有意に改善したことが示されています(代表文献h)。この研究は、炎症後色素沈着の治療におけるトレチノインの安全性と有効性を裏付けています。
◉補足コメント:
レチノイドが美白剤??と思われるでしょうが、肝斑、炎症後色素沈着に対して単独使用の臨床試験があり、効果が証明されている以上、ChatGPTが美白剤と判断するのも当然かもしれません。
▶クリニックで取り扱うトレチノイン
◉代表文献:
さすがに第4位になると代表文献のジャーナルの権威性も段違いです。
h) Topical tretinoin (retinoic acid) therapy for hyperpigmented lesions caused by inflammation of the skin in black patients
S M Bulengo-Ransby, et al.
N Engl J Med
1993 May 20;328(20):1438-43
第3位 アゼライン酸
当院で肝斑治療に使用しているアゼライン酸が第3位です。
アゼライン酸はニキビ、色素沈着、赤ら顔の治療に使われます。大人ニキビができやすく、そのたびに色素沈着になって困っている方に最適です。
◉作用機序:
アゼライン酸の美白作用の作用機序は、主に以下の点に起因すると考えられます。
1 チロシナーゼの阻害:アゼライン酸は、メラニン生成に関与する主要酵素であるチロシナーゼを直接的かつ競合的に阻害します。
2 メラノサイトへの選択的抑制効果:アゼライン酸は、特に過活動性メラノサイトに対して選択的な抑制効果を示します。
3 活性酸素種(ROS)の産生抑制と抗酸化作用
◉ランキングの根拠:
高評価につながったのは、他の美白剤と比べ明らかに大規模なランダム比較試験でハイドロキノンと同等という結果を出していることが大きいでしょう。
文献自体はやや古めですが、対象人数が329人で、観察期間が24週という大規模かつ長期の二重盲検試験で、ハイドロキノンと同等の効果を証明しています(代表文献i)。
◉補足コメント:
アゼライン酸は肌への刺激が軽度で、ほとんどの人が安心して使い続けられるのが特徴です。文献的には妊娠中の使用も安全とされています。
またアゼライン酸は抗菌作用もありますが、一般的な抗生物質とは異なり耐性を生じないとされています。
▶クリニックで取り扱うアゼライン酸
◉代表文献:
i) The treatment of melasma. 20% azelaic acid versus 4% hydroquinone cream
L M Baliña, K Graupe
Int J Dermatol
1991 Dec;30(12):893-5
第2位 チアミドール
チアミドールはドイツの Beiersdorf(バイヤスドルフ)が開発した美白成分です。
◉作用機序:
チアミドールの美白作用の作用機序は、チロシナーゼ酵素の活性を阻害することです:
◎チロシナーゼ酵素の阻害: チロシナーゼは、皮膚の過剰な色素沈着の治療において阻害標的となる酵素です。これは、メラニン生成における律速酵素であるためです。
◎ヒトチロシナーゼへの特異性: 多くの市販のチロシナーゼ阻害剤の臨床的有効性は限られており、これは主に、標的としてヒトチロシナーゼではなくマッシュルームチロシナーゼに対して試験されたためです。しかし、チアミドールは、50,000以上の化合物のスクリーニングの結果、ヒトチロシナーゼの特に強力な阻害剤として特定されました。
◎他の阻害剤に対する優位性: 試験管内(in vitro)では、チアミドールは、アルブチン、コウジ酸、ハイドロキノンなどの一般的に使用される過剰色素沈着阻害剤よりも優れていることが示されています。
◉ランキングの根拠:
新しい美白成分なので臨床試験の数も多くありませんが、肝斑にも炎症後色素沈着にも有意な改善をもたらすことが示されています。ハイドロキノンとの比較で言うと、2%ハイドロキノンより効果的、4%ハイドロキノンとは同等の効果という評価です。
肝斑がある女性50人を対象にした0.2%チアミドールと4%ハイドロキノンを比較した90日間の試験で、チアミドール群では84%、ハイドロキノン群では74%で改善を認めました。有意差は認められませんでした(代表文献j)。
◉補足コメント:
昨年の肝斑のレビュー文献でも、「チアミドールは、肝斑の治療薬としてハイドロキノンに匹敵する可能性がある」と高い評価を受けています(代表文献f)。美白剤の王座をハイドロキノンから奪えるとしたら、このチアミドールかもしれません。
ハイドロキノンと比較して、重篤な副作用や色素沈着の悪化のリスクが低く、安全な治療選択肢であると考えられます。
◉代表文献:
j) Efficacy and safety of topical isobutylamido thiazolyl resorcinol (Thiamidol) vs. 4% hydroquinone cream for facial melasma: an evaluator-blinded, randomized controlled trial
P B Lima, et al.
J Eur Acad Dermatol Venereol
2021 Sep;35(9):1881-1887
第1位 ハイドロキノン
ハイドロキノンは、数十年にわたる臨床使用の歴史と、最も広範な臨床文献に裏打ちされ、第1位にランクされました。
◉作用機序:
ハイドロキノン(HQ)の美白剤としての作用機序は、主に以下の点が挙げられます。
◎チロシナーゼ酵素の阻害:
HQの主要な作用機序は、メラニン生成に関与する酵素であるチロシナーゼを阻害することです。チロシナーゼは、アミノ酸のチロシンをメラニン前駆体に変換する作用を触媒します。HQが存在すると、チロシナーゼはチロシンよりもHQを優先的に酸化するため、メラニンが生成されません。
◎メラノサイトの構造および機能の改変(細胞毒性):
ハイドロキノン(HQ)は、メラニン生成に関わる酵素であるチロシナーゼを阻害するだけでなく、メラノサイトの構造と機能も変化させることで色素過剰症を軽減します。
◉ランキングの根拠:
安全性への懸念が存在するものの、その証明された強力な有効性と圧倒的なエビデンスの蓄積量は、依然として他の追随を許しません。
今回のランキング作成に当たっては、文献のエビデンスを判定するために臨床ガイドライン作成などで国際的に広く使われているGRADE(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)システム を活用しました。
GRADEでは高(High)、中(Moderate)、低(Low)などと評価しますが、ハイドロキノンは唯一の高(High)評価でした。ちなみに高(High)とは「新たな研究が出ても結論が大きく変わる可能性は低い。」ことを意味します。
◉補足コメント:
美白効果を称賛される一方で、ハイドロキノンは副作用のリスクを内包しています。そのため米国では2020年10月以降、ハイドロキノンが配合されたコスメの販売はできなくなりました。
その背景には美白剤の「ゴールドスタンダード」ハイドロキノンならではの「濫用」の問題があります。
肌の色が黒く生まれた人が白くしたいという理由で、高濃度のハイドロキノンを長期間にわたり自己判断で使って副作用を引き起こす事例が実は世界中で後をたちません。
そのため米国だけでなく世界的に見ても、化粧品への配合は禁止される流れになっています(日本では化粧品の配合が許されています)。
ハイドロキノンの使用は、医師の監督下で、計画的な治療サイクルに基づいて行われるべきです。
▶クリニックで取り扱うハイドロキノン
◉代表文献:
代表文献として選んだのは、米国での2006年の行政による「ハイドロキノンを含むコスメの禁止提案」に対し、全米屈指のニューヨーク市のマウント・サイナイ病院の皮膚科の臨床教授が、詳細に安全性データを吟味して規制に反対したレビュー文献です(代表文献k)。米国皮膚科学会公式ジャーナルが掲載しています。
k) The safety of hydroquinone: A dermatologist's response to the 2006 Federal Register
Jacob Levitt
J Am Acad Dermatol
2007 Nov;57(5):854-72
結局、米国では2020年にハイドロキノンを含むコスメの販売は事実上禁止されました。ただし処方薬としての使用は継続され、今も「医師の管理下で最も有効な美白剤」との位置づけは維持されています。
クリニックで取り扱う美白剤
おすすめの「美白」関連記事
##今回ランキング作成にあたり使用したプロンプト##
役割
あなたは、皮膚科領域のエビデンス合成(systematic review & evidence grading)を専門とする研究者です。依頼者は臨床家です。依頼者の臨床意思決定を支えるため、**皮膚の炎症後色素沈着(PIH)と肝斑(melasma)に対する外用(topical)“単剤”**の治療効果を、最新の学術文献に基づいて比較し、**客観的指標とGRADEで評価したランキング(Top 10)**を作成してください。
ゴール
1PIH用 Top 10 と 肝斑用 Top 10 を別々に作成(重複可)。
2可能なら**“総合(PIHと肝斑を横断)Top 10”**も提示。
3各有効成分ごとに順位・理由・根拠文献(代表RCT/対照試験の主要3本まで)を明示。
4エビデンスの質はGRADE(High/Moderate/Low/Very low)で提示。
重要:該当する単剤RCT/対照試験が十分でない場合は、ランキングに無理に入れず「エビデンス不足」として別枠に列挙。Top 10に満たない場合は該当数のみ提示。
対象・定義
・対象疾患:PIH、肝斑(各々で評価)。
・介入:**外用“単剤”**の美白/色素改善成分(例:ハイドロキノン、アゼライン酸、ナイアシンアミド、コウジ酸、アルブチン、トラネキサム酸外用、システアミン、メキノール、4-n-ブチルレゾルシノール/チアミドール、ビタミンC誘導体 等)。
・対照:プラセボ/車両、無治療、または有効成分比較。
・アウトカム(客観指標を優先):
色差計/分光測色(L*a*b*、ΔL*、ITA°)、メラニンインデックス、
MASI/mMASI(肝斑)、客観スコア(BSA、デジタル画像解析)、
有害事象(刺激感、皮膚炎等)、治療中止率、再発率。
・対象皮膚タイプ:Fitzpatrick I–VI(IV–VIへの外的妥当性も評価項目に入れる)。
除外基準(厳守)
・コンビネーション療法(例:Kligman/トリプルセラピー、ハイドロキノン+トレチノイン等)は除外。
・内服・注射・点滴は除外(トラネキサム酸は外用単剤の試験のみ評価)。
・手技系(化学ピーリング、レーザー、光治療、マイクロニードリング等)やサンスクリーン単独も除外(ただし併用の有無はリスク・オブ・バイアスとして言及)。
・症例報告や非比較研究のみはランキング対象外(補足に回す)。
文献収集と選別
・一次情報を最優先:RCT、盲検化、対照群ありを重視。
・データベース:PubMed/MEDLINE、Embase、Cochrane、J‑STAGE等。検索日を明記。
・言語:日本語・英語(他言語も要約可)。
・同一試験の重複出版は1件に統合。
・事前登録/プロトコルの有無、サンスクリーン使用の均衡、追跡期間も抽出。
エビデンス評価(GRADE+スコアリング)
1 GRADE:High / Moderate / Low / Very low(リスク・オブ・バイアス、非一貫性、間接性、不精確性、出版バイアス;大効果・用量反応でのアップグレード可)。
2 **総合スコア(0–13点)**でランキングを算出:
○研究の質(GRADEを点数化):High=3, Moderate=2, Low=1, Very low=0
○効果量(SMDまたは群間差の標準化):なし/極小=0、小=1(≈0.2)、中=2(≈0.5)、大=3(≈0.8)、非常に大=4(>0.8)
○再現性/一貫性:独立RCT数やメタ解析の有無:0–3
○客観アウトカムの採用(測色/MI/MASI等):0 or 1
○フォトタイプIV–VIの裏付け:0 or 1
○安全性(AEによる中止や重篤事象):+1(概ね良好)、0、−1(有害事象多い)
3 同点時のタイブレーク:①GRADEが高い>②効果量が大きい>③フォトタイプ外的妥当性>④安全性>⑤最新性。
可能なら**効果量の算出根拠(平均差/SD、SMD、信頼区間、I²)**を簡潔に提示。
出力要件(必須)
・表形式(日本語)+ 機械可読JSON の両方を出力。
・PIH Top 10、肝斑 Top 10、(任意で)総合Top 10の順に提示。
・各成分ごとに以下を1エントリで記載:
[表エントリ項目]
Rank/有効成分(日本語名 / 英語名 / 同義語)
適応:PIH/肝斑(該当に✔)
推奨濃度域・用法(根拠試験のレンジと期間)
主要アウトカム(例:ΔL*、mMASI、MI 等)と効果量(SMD/群間差、95%CI)
GRADE(High/Mod/Low/VLow)
総合スコア(0–13) 内訳(例:3+3+2+1+1+1=11)
安全性要約(刺激性/PIH悪化の有無、離脱率)
代表文献(最大3件):著者・年・誌名・試験デザイン・N・期間・PMID/DOI
要約(なぜこの順位か:2–3行)
[JSONスキーマ(例)]{ "condition": "PIH | Melasma | Overall", "updated_on": "YYYY-MM-DD", "rankings": [ { "rank": 1, "agent": { "jp": "ハイドロキノン", "en": "Hydroquinone", "synonyms": ["HQ"] }, "indication": ["PIH","Melasma"], "dose_range": "2–4% cream, qHS", "duration_range_weeks": "8–24", "outcomes": [{"metric":"ΔL*","effect_size_SMD":0.85,"CI":"0.60–1.10"}], "GRADE": "High", "score_breakdown": {"GRADE":3,"effect":3,"consistency":3,"objective":1,"phototype":1,"safety":0}, "total_score": 11, "safety": "軽度刺激、接触皮膚炎まれ。長期高濃度で外因性黒皮症の報告あり。", "key_refs": [{"author":"…","year":2020,"journal":"…","PMID":"…","DOI":"…"}], "rationale_jp": "…" } ], "insufficient_evidence": ["成分名A","成分名B"]}
追加指示
図表の明確化:指標(L*、mMASI、MI)の**方向(改善=数値の増減どちらか)**を明記。
サンスクリーン:介入群・対照群での取扱いが均衡でない場合はリスク・オブ・バイアスとして言及。
重複回避:同一製剤の異名・誘導体は薬理学的に区別し、別分子は別エントリ。
ブランド名の最小化:基本は一般名で記載。
透明性:検索式、期間、除外理由を簡潔に付記(数行で可)。
臨床翻訳:最終セクションで、誰に・どの状況で有益になりやすいか(例:フォトタイプIV–VIのPIH での実効性)を1段落に要約。
期待する最終セクション(短い総括)
要約:上位3成分の共通点(客観指標での一貫した効果、再現性)
ギャップ:エビデンス不足の領域(例:特定フォトタイプ/長期安全性)
実装上の注意:刺激性対策、使用期間の目安、再発管理の示唆(文献準拠)
品質基準
・正確性>網羅性>簡潔性。
・引用はPMIDまたはDOI必須、可能ならページ/図表番号。
・直接比較のない成分間は効果量の標準化で比較。恣意的判断を避ける。
・断定的表現はGRADEと効果量で裏づける。

制作・執筆:坂田修治(医師:美容外科・美容皮膚科 青い鳥 院長)
(最終更新日:2025年12月12日)